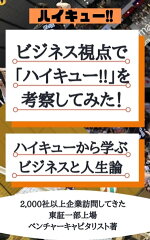【今日の気になったニュース・記事】
2,000社以上の経営者と面談した、元東証一部上場のベンチャーキャピタリストが厳選!
新旧問わずに、その日、気になったニュースをピックアップ!
新しいニュースから、古い記事まで「新たな発見」をお届けいたします。
【本日のニュース・記事】
■三島由紀夫「切腹自殺」から50年、彼が憂えた日本はどう変わったか
~11月25日は50回目の「憂国忌」~
週刊現代(講談社)2020/11/20
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77545
~~~
三島は現在の日本をどう思うのか
11月25日、三島の命日に毎年必ず開かれてきた「憂国忌」が50回目を迎える。
三島が生前に認めた檄文には、こうある。
「われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。
政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善の身に捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を潰してゆくのを歯噛みをしながら見ていなければならなかった」
おそらく、来たる25日、憂国忌の登壇者の言葉には、三島の予想通りになりつつある日本を憂える気持ちと、50年も惰眠を貪ってしまったという痛恨の念が交錯するのではないか。
もし、三島が現在の日本、いや、世界を見たら、何と言うだろう。三島自害の意味をもう一度振り返ることは、まさに乱世の今、非常に有意義なことではないかと想像する。
~~~
■三島由紀夫「切腹自殺」から50年、彼が憂えた日本はどう変わったか~11月25日は50回目の「憂国忌」~
週刊現代(講談社)2020/11/20
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77545
どこかタブー視されている三島由紀夫氏。
今から50年前、1970年〈昭和45年〉11月25日、三島由紀夫氏は自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ、バルコニーでクーデターを促す演説をしたのち、割腹自殺を遂げました。
2020年11月25日、三島由紀夫没後50年を迎えました。
多くの人は一度くらい、その名前だけはどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。
ただ、実際三島由紀夫という名前でイメージする人物像は「右翼」の「行き過ぎた人」という印象も多いのかもしれません。
タブー視されているところもあるのではないでしょうか。
実際、私もその一人でした。
しかしながら、改めて「没後50年」というキャッチコピーに誘われて、敢えて少し調べてみました。
以下、三島由紀夫氏の概略です。
~~~
三島由紀夫。
本名:平岡 公威〈ひらおか きみたけ〉。
1925年〈大正14年〉1月14日生まれ。
小説家・劇作家・随筆家・評論家・政治活動家。
戦後の日本文学界を代表する作家の一人であると同時に、ノーベル文学賞候補になるなど、日本語の枠を超え、海外においても広く認められた作家。
『Esquire』誌の「世界の百人」に選ばれた初の日本人で、国際放送されたテレビ番組に初めて出演した日本人でもある。
三島由紀夫の生涯
1925年(大正14年)1月14日、東京市四谷区永住町2番地において、父・平岡梓(当時30歳)と母・倭文重(当時19歳)の間の長男として誕生。
「公威」の名は祖父・定太郎による命名で、定太郎の恩人で同郷の土木工学者・古市公威にあやかって名付けられた。
家は借家であったが同番地内で一番大きく、かなり広い和洋折衷の二階家で、家族のほかに女中6人と書生や下男が居た。
兄弟は、3年後に妹・美津子、5年後に弟・千之が生まれた。
父・梓は、一高から東京帝国大学法学部を経て、高等文官試験に1番で合格したが、面接官に悪印象を持たれて大蔵省入りを拒絶され、農商務省に勤務していた。岸信介、我妻栄、三輪寿壮とは一高、帝大の同窓であった。
母・倭文重は、加賀藩藩主・前田家に仕えていた儒学者・橋家の出身。父(三島の外祖父)は東京開成中学校の5代目校長で、漢学者・橋健三。
祖父・定太郎は、兵庫県印南郡志方村大字上富木の農家の生まれ。帝国大学法科大学を卒業後、内務省に入省し内務官僚となる。
1893年(明治26年)、武家の娘である永井夏子と結婚し、福島県知事、樺太庁長官などを務めたが、疑獄事件で失脚した(のちに無罪判決)。
祖母・夏子は、父・永井岩之丞(大審院判事)と、母・高の間に長女として生まれた。夏子の母方の祖父・松平頼位の血筋を辿っていくと徳川家康に繋がっている。
夏子は12歳から17歳で結婚するまで有栖川宮熾仁親王に行儀見習いとして仕えた。夏子の祖父は江戸幕府若年寄の永井尚志。
なお、永井岩之丞の同僚・柳田直平の養子が柳田国男で、平岡定太郎と同じ兵庫県出身という縁もあった柳田国男は、夏子の家庭とは早くから交流があった。
作家・永井荷風の永井家と夏子の実家の永井家は同族で、夏子の9代前の祖先永井尚政の異母兄永井正直が荷風の12代前の祖先にあたる。
祖父、父、そして息子の三島由紀夫と、三代に渡って同じ大学の学部を卒業した官僚の家柄であった。
江戸幕府の重臣を務めた永井尚志の行政・統治に関わる政治は、平岡家の血脈や意識に深く浸透したのではないかと推測される。
公威と祖母・夏子とは、学習院中等科に入学するまで同居し、公威の幼少期は夏子の絶対的な影響下に置かれていた。
歌舞伎、谷崎潤一郎、泉鏡花などの夏子の好みは、後年の公威の小説家および劇作家としての素養を培った。
1931年(昭和6年)4月、公威は学習院初等科に入学した。
読書に親しみ、世界童話集、印度童話集、『千夜一夜物語』、小川未明、鈴木三重吉、ストリンドベルヒの童話、北原白秋、フランス近代詩、丸山薫や草野心平の詩、講談社『少年倶楽部』、『スピード太郎』などを愛読した。
6年生の時の1936年(昭和11年)には、2月26日に二・二六事件があった。
6月には、〈非常な威厳と尊さがひらめいて居る〉と日の丸を表現した作文「わが国旗」を書いた。
公威は文芸部に入り、同年7月、学習院校内誌『輔仁会雑誌』159号に作文「春草抄――初等科時代の思ひ出」を発表。
自作の散文が初めて活字となった。
以後、『輔仁会雑誌』には、中等科・高等科の約7年間で多くの詩歌や散文作品、戯曲を発表することとなる。
11、12歳頃、ワイルドに魅せられ、やがて谷崎潤一郎、ラディゲなども読み始めた。
7月に盧溝橋事件が発生し、日中戦争となった。
1938年(昭和13年)1月頃、初めての短編小説「酸模(すかんぽ)――秋彦の幼き思ひ出」を書き、同時期の「座禅物語」などとともに3月の『輔仁会雑誌』に発表された。
1939年(昭和14年)9月、ドイツ対フランス・イギリスの戦争が始まった(第二次世界大戦の始まり)。
1941年(昭和16年)4月、中等科5年に進級した公威は、7月に「花ざかりの森」を書き上げ、国語教師の清水文雄に原稿を郵送し批評を請うた。
清水は、「私の内にそれまで眠っていたものが、はげしく呼びさまされ」るような感銘を受け、自身が所属する日本浪曼派系国文学雑誌『文藝文化』の同人たちにも読ませるため、静岡県の伊豆修善寺温泉の新井旅館での一泊旅行を兼ねた編集会議に、その原稿を持参した。
「花ざかりの森」を読んだ彼らは、「天才」が現われたことを祝福し合い、同誌掲載を即決した。
筆名を考えている時、清水たちの脳裏に「三島」を通ってきたことと、富士の白雪を見て「ゆきお」が思い浮かんできた。
帰京後、清水が筆名使用を提案すると、公威は当初本名を主張したが受け入れ、「伊藤左千夫(いとうさちお)」のような万葉風の名を希望した。
結局「由紀雄」とし、「雄」の字が重すぎるという清水の助言で、「三島由紀夫」となった。
「由紀」は、大嘗祭の神事に用いる新穀を奉るため選ばれた2つの国郡のうちの第1のものを指す「由紀」(斎忌、悠紀、由基)の字にちなんで付けられた。
「花ざかりの森」は、『文藝文化』昭和16年9月号から12月号に連載された。
この年になり行われた南部仏印進駐以降、次第にイギリスやアメリカとの全面戦争突入が濃厚、12月8日に行われたマレー作戦によって日本はついにイギリスやアメリカ、オランダなどの連合国と開戦となった(大東亜戦争)。
各地で日本軍が勝利を重ねていた同年4月、大東亜戦争開戦の静かな感動を厳かに綴った詩「大詔」を『文藝文化』に発表。
1943年(昭和18年)2月24日、公威は学習院輔仁会の総務部総務幹事となった。
日本軍とイギリス軍やアメリカ軍との戦争が激化していく中、公威は〈アメリカのやうな劣弱下等な文化の国、あんなものにまけてたまるかと思ひます〉、〈米と英のあの愚人ども、俗人ども、と我々は永遠に戦ふべきでせう。俗な精神が世界を蔽うた時、それは世界の滅亡です〉と神聖な日本古代精神の勝利を願った。
1944年(昭和19年)4月27日、公威も本籍地・兵庫県印南郡志方村村長発信の徴兵検査通達書を受け取り、5月16日、兵庫県加古郡加古川町の加古川公会堂で徴兵検査を受けた。
結果は第二乙種で合格となった。
1944年(昭和19年)9月9日、学習院高等科を首席で卒業。
卒業生総代となった。
卒業式には昭和天皇が臨席し、宮内省より陛下からの恩賜の銀時計を拝受され、ドイツ大使からはドイツ文学の原書3冊をもらった。
御礼言上に、学習院長・山梨勝之進海軍大将と共に宮内参内し、謝恩会で華族会館から図書数冊も贈られた。
大学は文学部への進学という選択肢も念頭にはあったものの、父・梓の説得により、同年10月1日には東京帝国大学法学部法律学科(独法)に入学(推薦入学)した。
1945年(昭和20年)、いよいよ戦況は逼迫して大学の授業は中断され、公威は1月10日から「東京帝国大学勤労報国隊」として、群馬県新田郡太田町の中島飛行機小泉製作所に勤労動員され、総務部調査課配属となった。
風邪で寝込んでいた母から移った気管支炎による眩暈や高熱の症状を出していた公威は、入隊検査の折、新米の軍医からラッセルが聞こえるとして肺浸潤と誤診され、即日帰郷となった。
その部隊の兵士たちはフィリピンに派遣され、多数が死傷してほぼ全滅した。
戦死を覚悟していたつもりが、医師の問診に同調したこの時のアンビバレンスな感情が以後、三島の中で自問自答を繰り返す。
1945年(昭和20年)5月5日から、東京よりも危険な神奈川県高座郡大和の海軍高座工廠に勤労動員された。
1945年(昭和20年)8月6日、9日と相次ぎ、広島と長崎に原爆が投下された。
1946年(昭和21年)1月1日、昭和天皇が「人間宣言」の詔書を発した。
GHQによる占領下の日本では、戦犯の烙印を押された軍人が処刑されただけでなく、要職にいた各界の人間が公職追放になった。
マスコミや出版業界も「プレスコード」と呼ばれる検閲が行われ、日本を賛美することは許されなかった。
戦時中に三島が属していた日本浪曼派の保田與重郎や佐藤春夫、その周辺の中河与一や林房雄らは、戦後に左翼文学者や日和見作家などから戦争協力の「戦犯文学者」として糾弾された。
役人になることを考えた三島は、同月から高等文官試験を受け始めた。
1947年(昭和22年)11月28日、三島は東京大学法学部法律学科を卒業した。
卒業前から受けていた様々な種類の試験をクリアし、12月13日に高等文官試験に合格した三島は、12月24日から大蔵省に初登庁し、大蔵事務官に任官されて銀行局国民貯蓄課に勤務することになった。
大蔵省に入省してすぐの頃、文章力を期待された三島は、国民貯蓄振興大会での大蔵大臣(栗栖赳夫)の演説原稿を書く仕事を任された。
三島は創作に専念するため大蔵省に辞表を提出し、「依願免本官」という辞令を受けて退職した。
長編『盗賊』が真光社から刊行され、12月1日には短編集『夜の仕度』が鎌倉文庫から刊行された。
1949年(昭和24年)2月24日、作家となってから初上演作の戯曲『火宅』が俳優座により初演され、従来のリアリズム演劇とは違う新しい劇として、神西清や岸田国士などの評論家から高い評価を受けた。
長編『仮面の告白』は出版され、発売当初は反響が薄かったものの、10月に神西清が高評した後、花田清輝に激賞されるなど文壇で大きな話題となった。
年末にも読売新聞の昭和24年度ベストスリーに選ばれ、作家としての三島の地位は不動のものとなった。
長編『潮騒』は、1954年(昭和29年)6月10日に新潮社から出版されるとベストセラーとなり、すぐに東宝で映画化されて三船敏郎の特別出演もキャスティングされた。
三島はこの作品で第1回新潮社文学賞を受賞するが、これが三島にとっての初めての文学賞であった。
これを受け、2年後にはアメリカ合衆国でも『潮騒』の英訳(The Sound of the Waves)が出版されベストセラーとなり、三島の存在を海外でも知られるきっかけの作品となった。
「金閣寺」は、1956年(昭和31年)1月から『新潮』に連載開始され、10月に『金閣寺』が新潮社から刊行された。
傑作の呼び声高い作品として多数の評論家から高評価を受けた『金閣寺』は三島文学を象徴する代表作となり、第8回読売文学賞も受賞した。
それまで三島に懐疑的だった評者からも認められ、三島は文壇の寵児となった。
この時期の三島は、『金閣寺』のほかにも、『永すぎた春』や『美徳のよろめき』などのベストセラー作品を発表し、そのタイトルが流行語になった。
川端康成を論じた『永遠の旅人』も好評を博し、戯曲でも『白蟻の巣』が第2回岸田演劇賞を受賞、人気戯曲『鹿鳴館』も発表されるなど、旺盛な活動を見せ、戯曲集『近代能楽集』(「邯鄲」「綾の鼓」「卒塔婆小町」「葵上」「班女」を所収)も刊行された。
1961年(昭和36年)1月は、二・二六事件に題材をとり、のちに自身で監督・主演で映画化する「憂国」を『小説中央公論』に発表。
また、『仮面の告白』や『金閣寺』も英訳出版されるなど、海外での三島の知名度も上がった時期で、「世界の文豪」の1人として1963年(昭和38年)12月17日のスウェーデンの有力紙『DAGENUS NYHETER』に取り挙げられ、翌1964年(昭和39年)5月には『宴のあと』がフォルメントール国際文学賞で2位となり、『金閣寺』も第4回国際文学賞で第2位となった。
国連事務総長だったダグ・ハマーショルドも1961年(昭和36年)に赴任先で事故死する直前に『金閣寺』を読了し、ノーベル財団委員宛ての手紙で大絶賛した。
1966年(昭和41年)10月には自衛隊体験入隊を希望し、防衛庁関係者や元陸将・藤原岩市などと接触して体験入隊許可のための仲介や口利きを求め、12月には舩坂弘の著作の序文を書いた返礼として日本刀・関ノ孫六を贈られた。
4月12日から約1か月半、単身で自衛隊に体験入隊した三島は、イギリスやノルウェー、スイスなどの民兵組織の例に習い、国土防衛の一端を担う「祖国防衛隊」構想を固めた後、学生らを引き連れて自衛隊への体験入隊を定期的に行なった。
以降、三島は航空自衛隊のF-104戦闘機への搭乗体験や、陸上自衛隊調査学校情報教育課長・山本舜勝とも親交し、共に民兵組織(のち「楯の会」の名称となる)会員への指導を行うことになる。
三島は、企業との連携で「祖国防衛隊」の組織拡大を目指し、民族資本から資金を得て法制化してゆく「祖国防衛隊構想」を立ち上げ、経団連会長らと何度か面談していたが、面談を最後に資金援助を断られてしまった。
同年10月21日の国際反戦デーにおける新左翼の新宿騒乱の激しさから、彼らの暴動を鎮圧するための自衛隊治安出動の機会を予想した三島は、それに乗じて「楯の会」が斬り込み隊として加勢する自衛隊国軍化・憲法9条改正へのクーデターを計画した。
この頃、三島はすでに何人かの楯の会会員らに居合を習わせ、先鋭の9名(持丸博、森田必勝、倉持清、小川正洋、小賀正義など)に日本刀を渡し、「決死隊」を準備していた。
しかし、7月下旬頃から古参メンバーの中辻や万代と、雑誌『論争ジャーナル』の資金源を巡って齟齬が生じ、8月下旬に彼らを含む数名が楯の会を正式退会した。
この年の10月21日の国際反戦デーの左翼デモは前年とは違い、前もって配備されていた警察の機動隊によって簡単に鎮圧された。
三島は自衛隊治安出動が不発に終わった絶望感から、未完で終わるはずだった「暁の寺」を〈いひしれぬ不快〉で書き上げた。
これで、クーデターによる憲法改正と自衛隊国軍化を実現する〈作品外の現実〉に賭けていた夢はなくなった。
新聞では、「果たし得てゐない約束」と題して自身の戦後25年間を振り返り、〈その空虚に今さらびつくりする。私はほとんど「生きた」とはいへない。鼻をつまみながら通りすぎたのだ〉と告白し、〈私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行つたら「日本」はなくなつてしまうのではないかといふ感を日ましに深くする〉と戦後社会への決別を宣言した。
同じ7月、三島は保利茂官房長官と中曽根康弘防衛庁長官に『武士道と軍国主義』『正規軍と不正規軍』という防衛に関する文書を政府への「建白書」として託したが、中曽根に阻止されて閣僚会議で佐藤栄作首相に提出されず葬られた。
1970年(昭和45年)11月25日、三島は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内東部方面総監部の総監室を森田必勝ら楯の会会員4名と共に訪れ、面談中に突如、益田兼利総監を人質にして籠城すると、バルコニーから檄文を撒き、自衛隊の決起を促す演説をした直後に割腹自決した。
三島の辞世の句は2句。
益荒男(ますらを)が たばさむ太刀の 鞘鳴りに 幾とせ耐へて 今日の初霜
散るをいとふ 世にも人にも 先駆けて 散るこそ花と 吹く小夜嵐
~~~
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
45歳没。
なぜか、タブー視されている三島由紀夫氏。
マスメディアは没50年についても、殆ど触れることはありません。
どこか「過去の人物」「昔の狂人」として、タブー視して取り扱っているように感じます。
ただ、それほど遠い人ではないのではないでしょうか。
あの美輪明宏さんや石原慎太郎さんとの交友もあったそうです。
中曽根元総理とのやりとりなども含めて「過去の人物」として遠ざけてしまうには、まだ早いような気もします。
しかしながら、ネットで「三島由紀夫」を検索すると、主要メディアの関連記事は殆どヒットしません。
Google検索の検閲でも?と感じてしまいますが、まだ「過去の人物」とするには、学ぶべきところは多いのではないでしょうか。
日本は、米国と中国、そしてロシアという大国に挟まれた地理的環境。
米中対立もあって、日本の立ち位置、立ち振る舞いは非常に難しくなっています。
日本そのものの価値が失われつつあると言えるのかもしれません。
米中対立がクローズアップされる中、「米国か」「中国か」という2者択一の論調ばかり。
「日本独自」という視点が忘れられているような気もします。
軍事力、経済力だけではありません。
IT技術も、米国と中国が世界を席巻し「日本発」のIT技術は殆ど見当たりません。
コロナ時代、人と接触するリスク低減のIT技術はさらにその重要性は増しています。
AmazonやYouTube、MicrosoftやGoogle、Netflixは、さらに日本国内の市場を独占してきています。
足元では、長年通い詰めたラーメン店が閉店、近隣の本屋さん、花屋さんなど、多くの零細企業がコロナ不況で消えていっています。
国際政治から私たちの生活に至るまで、あらゆるシーンで「日本の価値」そのものが低下しているのかもしれません。
私たち日本人は、今後、何を基準に、何を大切にし、何を目指し、何をもって、日本の子どもたちの未来を託すべきなのでしょうか。
三島由紀夫が憂いた未来。
今、その未来が実現しつつあるのかもしれません。
最後に「三島由紀夫の持論」、そして最期の「檄文」全文を記載いたします。
■三島由紀夫の持論
・自衛隊論
三島は、国の基本的事項である防衛を最重要問題と捉え、「日本国軍」の創立を唱えながら、「一定の領土内に一定の国民を包括する現実の態様」である国家という「一定空間の物理的保障」を守るには軍事力しかなく、もしもその際に外国の軍事力(核兵器その他)を借りるとしても、「決して外国の軍事力は、他国の時間的国家の態様を守るものではない」とし、日米安保に安住することのない日本の自主防衛を訴えている。
三島は1969年(昭和44年)の国際反戦デーの左翼デモの際に自衛隊治安出動が行われなかったことに関連し、「政体を警察力を以て守りきれない段階に来て、はじめて軍隊の出動によつて国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであらう」と説いており、その時々の「政体」を守る警察と、永久不変の日本の「国体」を守る国軍の違いについて言及している。
また、「改憲サボタージュ」が自民党政権の体質となっている以上、「改憲の可能性は右からのクーデターか、左からの暴力革命によるほかはないが、いずれもその可能性は薄い」と指摘し、本来は「祭政一致的な国家」であった日本が、現代では国際強調主義と世界連邦の線上に繋がる「遠心力的」な「統治的国家(行政権の主体)」と、日本の歴史・文化という時間的連続性が継承される「求心力」的な「祭祀的国家(国民精神の主体)」の二極に分離し、「後者が前者の背後に影のごとく揺曳してゐる」状態にあるとしている。
現状では自衛隊の最高指揮権が日本の内閣総理大臣でなく、最終的には「アメリカ大統領にあるのではないかといふ疑惑」があり、現憲法の制約下で統治的国家の「遠心力」と祭祀的国家の「求心力」による二元性の理想的な調和と緊張を実現するためには、日本国民がそのどちらかに忠誠を誓うかを明瞭にし、その選択に基づいて自衛隊を二分するべきだという以下のような「自衛隊二分論」を三島は説いている。
1.航空自衛隊の9割、海上自衛隊の7割、陸上自衛隊の1割で「国連警察予備軍」を編成し、対直接侵略を主任務とすること。この軍は統治国家としての日本に属し、安保条約によって集団安全保障体制にリンクする。根本理念は国際主義的であり、身分は国連事務局における日本人職員に準ずる。
2.陸上自衛隊の9割、海上自衛隊の3割、航空自衛隊の1割で「国土防衛軍」を編成し、絶対自立の軍隊としていかなる外国とも軍事条約を結ばない。その根本理念は祭祀国家の長としての天皇への忠誠である。対間接侵略を主任務とし、治安出動も行う。
2.の「国土防衛軍」には多数の民兵が含まれるとし、「楯の会」はそのパイオニアであるとしている。なお、三島は徴兵制には反対している。
三島は、自衛隊が単なる「技術者集団」や「官僚化」に陥らないためには、「武士と武器」、「武士と魂」を結びつける「日本刀の原理」を復活し、「武士道精神」を保持しなければならないとし、軍人に「セルフ・サクリファイス」(自己犠牲)が欠けた時、官僚機構の軍国主義に堕落すると説いている。
そして、戦後禁忌になってしまった、天皇陛下が自衛隊の儀仗を受けることと、連隊旗を直接下賜すること、文人のみの文化勲章だけでなく、自衛隊員への勲章も天皇から授与されることを現下の法律においても実行されるべきと提言し、隊員の忠誠の対象を明確にし、「天皇と軍隊を栄誉の絆でつないでおくこと」こそ、日本および日本文化の危機を救う防止策になると説いている。
「栄誉大権は単に文化勲章や一般の文官の勲章のみでなく、軍事的栄誉として自衛隊を国民が認めて、天皇が直接に自衛隊を総攬するような体制ができなくちゃいかん。それがないと、日本の民主主義は真に土着的な民主主義にはなり得ない。」
— 三島由紀夫「国家革新の原理――学生とのティーチ・イン その一」
・日米安保について
日米安保については、「安保賛成か反対かといふことは、本質的に私は日本の問題ではないやうな気がする」と三島は述べており、そうした問いは結局のところ、アメリカを選ぶか、中共・ソビエトを選ぶかという、本質的には日本というものの自主性が選べない状況の中での問題であり、当時の激しい安保反対運動(安保闘争)がひとまず落ちついた後の未来に、日本にとっての真の問いかけが大きな問題として出てくるとしている。
そして、そこで初めて「われわれは最終的にその問ひかけに直面するんぢやないか」と語っている。
「私に言はせれば安保賛成といふのはアメリカ賛成といふことで、安保反対といふのはソヴィエトか中共賛成といふことだと、簡単に言つちまへばさうなるんで、どつちの外国に頼るかといふ問題にすぎないやうな感じがする。そこには「日本とは何か」といふ問ひかけが徹底してないんぢやないか。私はこの安保問題が一応方がついたあとに初めて、日本とは何だ、君は日本を選ぶのか、選ばないのかといふ鋭い問ひかけが出てくると思ふんです。」
— 三島由紀夫「日本とは何か」
別の場の発言でも、安保賛成はアメリカ派で一種の「西欧派」であり、安保反対も中共・ソビエトという共産党系の「外国派」であるとし、「日本人に向かって、『おまえアメリカをとるか、ソビエトをとるか中共をとるか』といったら、ほんとうの日本人だったら態度を保留すると思う」と述べている。
そして、「国粋派というのは、そのどっちの選択にも最終的には加担していない」として、「まだ日本人は日本を選ぶんだという本質的な選択をやれないような状況」にあり、安保反対派(中共・ソビエト派)の運動が激化していた当時の状況においては、西欧派の自民党の歴史的な役割として、「西欧派の理念に徹して、そこでもって安保反対勢力と刺しちがえてほしい」という考えを福田赳夫に伝えたことを1969年時点で語っている。
また、日米安保に関連する沖縄の米軍基地問題についても三島は、日本人の心情として日本の国内に外国(アメリカ)の軍隊がいるということに対する反対意識は、イデオロギーを抜きにすれば一般国民のナショナリズムや愛国心に訴えるものがあるため、それを外来勢力の共産党系左翼(天皇制・国体破壊を目論む者)に利用されやすいという、日本独特の難しい状況も語っている。
「日本民族の独立を主張し、アメリカ軍基地に反対し、安保条約に反対し、沖縄を即時返還せよ、と叫ぶ者は、外国の常識では、ナショナリストで右翼であらう。ところが日本では、彼は左翼で共産主義者なのである。十八番のナショナリズムをすつかり左翼に奪はれてしまつた伝統的右翼の或る一派は、アメリカの原子力空母エンタープライズ号の寄港反対の左翼デモに対抗するため、左手にアメリカの国旗を、右手に日本の国旗を持つて勇んで出かけた。これではまるでオペラの舞台のマダム・バタフライの子供である。」
— 三島由紀夫「STAGE-LEFT IS RIGHT FROM AUDIENCE」
・核武装について
三島は、ナチスのユダヤ人虐殺と並ぶ史上最大の「虐殺行為」の被害を広島がアメリカから受けたにもかかわらず、日本人が「過ちは二度とくりかへしません」と原爆碑で掲げていることに疑問を呈し、「原爆に対する日本人の民族的憤激を正当に表現した文字は、終戦の詔勅の『五内為ニ裂ク』といふ一節以外に、私は知らない」と述べている。
そして、そうした「民族的憤激」や「最大の屈辱」を「最大の誇り」に転換するべく「東京オリンピックに象徴される工業力誇示」を進めてきた日本人だが、はたして「そのことで民族的憤激は解決したことになるだらうか」として、唯一の被爆国である日本こそが核武装する権利があるという見解を1967年(昭和42年)の時点で以下のように示している。
「日本人は、八月十五日を転機に最大の屈辱を最大の誇りに切りかへるといふ奇妙な転換をやつてのけた。一つはおのれの傷口を誇りにする“ヒロシマ平和運動”であり、もう一つは東京オリンピックに象徴される工業力誇示である。だが、そのことで民族的憤激は解決したことになるだらうか。いま、日本は工業化、都市化の道を進んでゐる。明らかに“核”をつくる文化を受入れて生きてゐる。日本は核時代に向ふほかない。単なる被曝国として、手を汚さずに生きて行けるものではない。
核大国は、多かれ少なかれ、良心の痛みをおさへながら核を作つてゐる。彼らは言ひわけなしに、それを作ることができない。良心の呵責なしに作りうるのは、唯一の被曝国・日本以外にない。われわれは新しい核時代に、輝かしい特権をもつて対処すべきではないのか。そのための新しい政治的論理を確立すべきではないのか。日本人は、ここで民族的憤激を思ひ起すべきではないのか。」
— 三島由紀夫「私の中のヒロシマ――原爆の日によせて」
また、日本の自主防衛に関連し、1969年(昭和44年)に受けたカナダのTVインタビューでも、「私は、多くの日本人が、日本での核の保有を認めるとは思いません」と悲観的な予想を示しながら、自衛隊を二分し予備軍が国連軍に加わることで「核兵器による武装が可能になる」と答えている。
そして自決前の『檄』の後半では、日本にとって不平等な核拡散防止条約 (NPT) のことも語っている。
「諸官に与へられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。(中略)国家百年の大計にかかはる核停条約は、あたかもかつての五・五・三の不平等条約の再現であることが明らかであるにもかかはらず、抗議して腹を切るジェネラル一人、自衛隊からは出なかつた。沖縄返還とは何か? 本土の防衛責任とは何か? アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。あと二年の内に自主性を回復せねば、左派のいふ如く、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう。」
— 三島由紀夫「檄」
この警告について西尾幹二は、三島が「明らかに核の脅威を及ぼしてくる外敵」を意識し、このままでよいのかと問いかけているとし、三島自決の6年前に中国が核実験に成功し、核保有の5大国としてNPTで特権的位置を占め、三島自決の1970年(昭和45年)に中国が国連に加盟して常任理事国となったことに触れながら、「国家百年の大計にかかはる」と三島が言った日本のNPTの署名(核武装の放棄)を政府が決断したのが、同年2月3日だった当時の時代背景を説明している。
そして、三島が「あと二年の内」と言った意味は、この2年の期間に日本政府とアメリカの間で沖縄返還を巡り、日本の恒久的な核武装放棄を要望するアメリカと中国の思惑などの準備と工作があり、日本の核武装放棄と代替に1972年(昭和47年)に佐藤栄作がノーベル平和賞を受賞し、表向き沖縄返還がなされたことで、自衛隊が「永遠にアメリカの傭兵として終る」ことが暗示されていたと西尾は解説している。
・特攻隊について
三島の天皇観は、国家や個人のエゴイズムを掣肘するファクター、反エゴイズムの代表として措定され、「近代化、あらゆる工業化によるフラストレイションの最後の救世主」として存在せしめようという考えであったが、三島の神風特攻隊への思いも、彼らの「没我」の純粋さへの賛美であり、美的天皇観と同じ心情に基づいている。
三島の考える「純粋」は、小説『奔馬』で多く語られているが、その中には「あくまで歴史は全体と考へ、純粋性は超歴史的なものと考へたがよいと思ひます」とあり、評論『葉隠入門』においても、政治的思想や理論からの正否と合理性を超えた純粋行為への考察がなされ、特攻隊の死についてもその側面からの言及がなされている。
三島は日本刀を「魂である」としていたが、特攻隊についても西欧・近代への反措定として捉えており、「大東亜戦争」についても、「あの戦争が日本刀だけで戦つたのなら威張れるけれども、みんな西洋の発明品で、西洋相手に戦つたのである。
ただ一つ、真の日本的武器は、航空機を日本刀のやうに使つて斬死した特攻隊だけである」としている。
この捉え方は、戦時中、三島が学生であった頃の文面にも見られる。
「僕は僕だけの解釈で、特攻隊を、古代の再生でなしに、近代の殲滅――すなはち日本の文化層が、永く克服しようとしてなしえなかつた「近代」、あの尨大な、モニュメンタールな、カントの、エヂソンの、アメリカの、あの端倪すべからざる「近代」の超克でなくてその殺傷(これは超克よりは一段と高い烈しい美しい意味で)だと思つてゐます。
「近代人」は特攻隊によつてはじめて「現代」といふか、本当の「われわれの時代」の曙光をつかみえた、今まで近代の私生児であつた知識層がはじめて歴史的な嫡子になつた。それは皆特攻隊のおかげであると思ひます。日本の全文化層、世界の全文化人が特攻隊の前に拝跪し感謝の祈りをさゝげるべき理由はそこにあるので、今更、神話の再現だなどと生ぬるいたゝへ様をしてゐる時ではない。全く身近の問題だと思ひます。」
— 平岡公威「三谷信宛ての葉書」(昭和20年4月21日付)
敗戦時に新聞などが、「幼拙なヒューマニズム」や「戦術」と称し、神風特攻隊員らを「将棋の駒を動かすやうに」功利、効能的に見て、特攻隊の精神がジャーナリズムにより冒涜されて「神の座と称号」が奪われてしまったことへの憤懣の手記も、ノートに綴っていた。
「我々が中世の究極に幾重にも折り畳まれた末世の幻影を見たのは、昭和廿年の初春であつた。人々は特攻隊に対して早くもその生と死の(いみじくも夙に若林中隊長が警告した如き)現在の最も痛切喫緊な問題から目を覆ひ、国家の勝利(否もはや個人的利己的に考へられたる勝利、最も悪質の仮面をかぶれる勝利願望)を声高に叫び、彼等の敬虔なる祈願を捨てゝ、冒瀆の語を放ち出した。」
— 平岡公威「昭和廿年八月の記念に」
また、三島は戦後に『きけ わだつみのこえ』が特攻隊員の遺書を「作為的」に編纂し、編者が高学歴の学生のインテリの文章だけ珍重して政治的プロパガンダに利用している点に異議を唱え、「テメエはインテリだから偉い、大学生がむりやり殺されたんだからかわいそうだ、それじゃ小学校しか出ていないで兵隊にいって死んだやつはどうなる」と唾棄している。
『きけ わだつみのこえ』を題材とした映画についても「いはん方ない反感」を感じたとし、フランス文学研究をしていた学生らが戦死した傍らにシャルル・ボードレールかポール・ヴェルレーヌの詩集の頁が風にちぎれているシーンが、ボードレールも墓の下で泣くであろうほど「甚だしくバカバカしい印象」だと酷評し、「日本人がボオドレエルのために死ぬことはないので、どうせ兵隊が戦死するなら、祖国のために死んだはうが論理的」であるとしている。
・愛国心について
「愛国心」という言葉に対し、三島は官製のイメージが強いとして「自分がのがれやうもなく国の内部にゐて、国の一員であるにもかかはらず、その国といふものを向こう側に対象に置いて、わざわざそれを愛するといふのが、わざとらしくてきらひである」とし、キリスト教的な「愛」(全人類的な愛)という言葉はそぐわず、日本語の「恋」や「大和魂」で十分であり、「日本人の情緒的表現の最高のもの」は「愛」ではなくて「恋」であると主張している。
「愛国心」の「愛」の意味が、もしもキリスト教的な愛ならば「無限定無条件」であるはずだから、「人類愛」と呼ぶなら筋が通るが、「国境を以て閉ざされた愛」である「愛国心」に使うのは筋が通らないとしている。
アメリカ合衆国とは違い、日本人にとって日本は「内在的即自的であり、かつ限定的個別的具体的」にあるものだと三島は主張し、「われわれはとにかく日本に恋してゐる。これは日本人が日本に対する基本的な心情の在り方である」としている。
「恋が盲目であるやうに、国を恋ふる心は盲目であるにちがひない。しかし、さめた冷静な目のはうが日本をより的確に見てゐるかといふと、さうも言へないところに問題がある。さめた目が逸したところのものを、恋に盲ひた目がはつきりつかんでゐることがしばしばあるのは、男女の仲と同じである。」
— 三島由紀夫「愛国心」
こうした日本人の中にある内在的・即自的なものを大事にする姿勢と相通じる考え方は、三島が18歳の時に東文彦に出した書簡の中にも見られ、「我々のなかに『日本』がすんでゐないはずがない」として以下のように述べている。
「「真昼」―― 「西洋」へ、気持の惹かされることは、決して無理に否定さるべきものではないと思ひます。真の芸術は芸術家の「おのづからなる姿勢」のみから生まれるものでせう。近頃近代の超克といひ、東洋へかへれ、日本へかへれといはれる。その主唱者は立派な方々ですが、なまじつかの便乗者や尻馬にのつた連中の、そここゝにかもし出してゐる雰囲気の汚ならしさは、一寸想像のつかぬものがあると思ひます。我々は日本人である。我々のなかに「日本」がすんでゐないはずがない。この信頼によつて「おのづから」なる姿勢をお互いに大事にしてまゐらうではござひませんか。」
— 平岡公威「東文彦宛ての書簡」(昭和18年3月24日付)
・国語教育論
三島は、戦後の政府によって1946年(昭和21年)に改定された現代かなづかいを使わず、自身の原稿は終生、旧仮名遣ひを貫いた。三島は、言葉にちょっとでも実用的な原理や合理的な原理を導入したらもうだめだと主張し、中国人は漢字を全部簡略化したために古典が読めなくなったとしている。
また、敗戦後に日本語を廃止してフランス語を公用語にすべきと発言した志賀直哉について触れ、「私は、日本語を大切にする。これを失つたら、日本人は魂を失ふことになるのである。戦後、日本語をフランス語に変へよう、などと言つた文学者があつたとは、驚くにたへたことである」と批判した。
国語教育についても、現代の教育で絶対に間違っていることの一つが「古典主義教育の完全放棄」だとし、「古典の暗誦は、決して捨ててならない教育の根本であるのに、戦後の教育はそれを捨ててしまつた。ヨーロッパでもアメリカでも、古典の暗誦だけはちやんとやつてゐる。これだけは、どうでもかうでも、即刻復活すべし」と主張している。
そして、中学生には原文でどんどん古典を読ませなければならないとし、古典の安易な現代語訳に反対を唱え、日本語の伝統や歴史的背景を無視した利便・実用第一主義を唾棄し、「美しからぬ現代語訳に精出してゐるさまは、アンチョコ製造よりもつと罪が深い。
みづから進んで、日本人の語学力を弱めることに協力してゐる」と文部省の役人や教育学者を批判し、自身の提案として「ただカナばかりの原本を、漢字まじりの読みやすい版に作り直すとか、ルビを入れるとか、おもしろいたのしい脚注を入れるとか、それで美しい本を作るとか」を先生たちにやってもらいたいと述べている。
三島は、日本人の古典教育が衰えていったのはすでに明治の官僚時代から始まっていたとし、文化が分からない人間(官僚)が日本語教育をいじり出して「日本人が古典文学を本当に味わえないような教育をずっとやってきた」と述べ、意味が分からなくても「読書百遍意おのずから通ず」で、小学生から『源氏物語』を暗唱させるべきだとしている。
また、『論語』の暗唱、漢文を素読する本当の教え方が大事だとし、支那古典の教養がなくなってから日本人の文章がだらしなくなり、「日本の文体」も非常に弱くなったとしている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
■三島由紀夫「檄文」全文
~~~
われわれ楯の会は、自衛隊によって育てられ、いわば自衛隊はわれわれの父でもあり、兄でもある。
その恩義に報いるに、このような忘恩的行為に出たのは何故であるか。
かえりみれば、私は四年、学生は三年、隊内で準自衛官としての待遇を受け、一片の打算もない教育を受け、又われわれも心から自衛隊を愛し、もはや隊の柵外の日本にはない「真の日本」をここに夢み、ここでこそ終戦後ついに知らなかった男の涙を知った。
ここで流したわれわれの汗は純一であり、憂国の精神を相共にする同志として共に富士の原野を馳駆した。
このことには一点の疑いもない。
われわれにとって自衛隊は故郷であり、生ぬるい現代日本で凛冽の気を呼吸できる唯一の場所であった。
教官、助教諸氏から受けた愛情は測り知れない。
しかもなお、敢えてこの挙に出たのは何故であるか。
たとえ強弁と云われようとも、自衛隊を愛するが故であると私は断言する。
われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。
政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。
われわれは今や自衛隊にのみ、真の日本、真の日本人、真の武士の魂が残されているのを夢みた。
しかも法理論的には、自衛隊は違憲であることは明白であり、国の根本問題である防衛が、御都合主義の法的解釈によってごまかされ、軍の名を用いない軍として、日本人の魂の腐敗、道義の頽廃の根本原因を、なしてきているのを見た。
もっとも名誉を重んずべき軍が、もっとも悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである。
自衛隊は敗戦後の国家の不名誉な十字架を負いつづけて来た。
自衛隊は国軍たりえず、建軍の本義を与えられず、警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず、その忠誠の対象も明確にされなかった。
われわれは戦後のあまりに永い日本の眠りに憤った。
自衛隊が目ざめる時こそ、日本が目ざめる時だと信じた。
自衛隊が自ら目ざめることなしに、この眠れる日本が目ざめることはないのを信じた。
憲法改正によって、自衛隊が建軍の本義に立ち、真の国軍となる日のために、国民として微力の限りを尽すこと以上に大いなる責務はない、と信じた。
四年前、私はひとり志を抱いて自衛隊に入り、その翌年には楯の会を結成した。
楯の会の根本理念は、ひとえに自衛隊が目ざめる時、自衛隊を国軍、名誉ある国軍とするために、命を捨てようという決心にあつた。
憲法改正がもはや議会制度下ではむずかしければ、治安出動こそその唯一の好機であり、われわれは治安出動の前衛となって命を捨て、国軍の礎石たらんとした。
国体を守るのは軍隊であり、政体を守るのは警察である。
政体を警察力を以て守りきれない段階に来て、はじめて軍隊の出動によって国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであろう。
日本の軍隊の建軍の本義とは、「天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守る」ことにしか存在しないのである。
国のねじ曲った大本を正すという使命のため、われわれは少数乍ら訓練を受け、挺身しようとしていたのである。
しかるに昨昭和四十四年十月二十一日に何が起ったか。
総理訪米前の大詰ともいうべきこのデモは、圧倒的な警察力の下に不発に終った。
その状況を新宿で見て、私は、「これで憲法は変らない」と痛恨した。
その日に何が起ったか。
政府は極左勢力の限界を見極め、戒厳令にも等しい警察の規制に対する一般民衆の反応を見極め、敢えて「憲法改正」という火中の栗を拾はずとも、事態を収拾しうる自信を得たのである。
治安出動は不用になった。
政府は政体維持のためには、何ら憲法と抵触しない警察力だけで乗り切る自信を得、国の根本問題に対して頬かぶりをつづける自信を得た。
これで、左派勢力には憲法護持の飴玉をしやぶらせつづけ、名を捨てて実をとる方策を固め、自ら、護憲を標榜することの利点を得たのである。
名を捨てて、実をとる! 政治家たちにとってはそれでよかろう。
しかし自衛隊にとっては、致命傷であることに、政治家は気づかない筈はない。
そこでふたたび、前にもまさる偽善と隠蔽、うれしがらせとごまかしがはじまった。
銘記せよ!
実はこの昭和四十四年十月二十一日という日は、自衛隊にとっては悲劇の日だった。
創立以来二十年に亘って、憲法改正を待ちこがれてきた自衛隊にとって、決定的にその希望が裏切られ、憲法改正は政治的プログラムから除外され、相共に議会主義政党を主張する自民党と共産党が、非議会主義的方法の可能性を晴れ晴れと払拭した日だった。
論理的に正に、この日を境にして、それまで憲法の私生児であつた自衛隊は、「護憲の軍隊」として認知されたのである。
これ以上のパラドックスがあろうか。
われわれはこの日以後の自衛隊に一刻一刻注視した。
われわれが夢みていたように、もし自衛隊に武士の魂が残っているならば、どうしてこの事態を黙視しえよう。
自らを否定するものを守るとは、何たる論理的矛盾であろう。
男であれば、男の衿がどうしてこれを容認しえよう。
我慢に我慢を重ねても、守るべき最後の一線をこえれば、決然起ち上るのが男であり武士である。
われわれはひたすら耳をすました。
しかし自衛隊のどこからも、「自らを否定する憲法を守れ」という屈辱的な命令に対する、男子の声はきこえては来なかった。
かくなる上は、自らの力を自覚して、国の論理の歪みを正すほかに道はないことがわかっているのに、自衛隊は声を奪われたカナリヤのように黙ったままだった。
われわれは悲しみ、怒り、ついには憤激した。
諸官は任務を与えられなければ何もできぬという。
しかし諸官に与えられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。
シヴィリアン・コントロールが民主的軍隊の本姿である、という。
しかし英米のシヴィリアン・コントロールは、軍政に関する財政上のコントロールである。
日本のように人事権まで奪はれて去勢され、変節常なき政治家に操られ、党利党略に利用されることではない。
この上、政治家のうれしがらせに乗り、より深い自己欺瞞と自己冒涜の道を歩もうとする自衛隊は魂が腐ったのか。
武士の魂はどこへ行ったのだ。
魂の死んだ巨大な武器庫になって、どこかへ行こうとするのか。
繊維交渉に当っては自民党を売国奴呼ばはりした繊維業者もあったのに、国家百年の大計にかかわる核停条約は、あたかもかつての五・五・三の不平等条約の再現であることが明らかであるにもかかわらず、抗議して腹を切るジエネラル一人、自衛隊からは出なかった。
沖縄返還とは何か?
本土の防衛責任とは何か?
アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。
あと二年の内に自主性を回復せねば、左派のいう如く、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう。
われわれは四年待った。
最後の一年は熱烈に待った。
もう待てぬ。
自ら冒涜する者を待つわけには行かぬ。
しかしあと三十分、最後の三十分待とう。
共に起って義のために共に死ぬのだ。
日本を日本の真姿に戻して、そこで死ぬのだ。
生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。
生命以上の価値なくして何の軍隊だ。
今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。
それは自由でも民主主義でもない。
日本だ。
われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。
これを骨抜きにしてしまった憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか。
もしいれば、今からでも共に起ち、共に死のう。
われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇えることを熱望するあまり、この挙に出たのである。
三島由紀夫
~~~